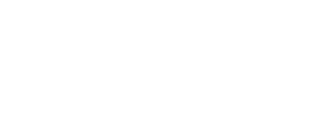前回の記事では、ユネスコ無形文化遺産に「伝統的酒造り」が登録され、どの様な点が登録に繋がったのかをお伝えしました。
今回は、より具体的に伝統的酒造りにより注目し、また現代の酒造りと比較しながら見ていきたいと思います。

まずはじめに・・
酒造りの始まりは約2000年前の弥生時代から、稲作文化と共に発展しました。
その当時の日本酒はまだ米を噛んで自然に発酵させる「口噛み酒」であり、麹菌の力を利用した発酵ではありませんでした。
その後、麹菌を使って米を発酵させる麹造りの原型が奈良時代(8世紀)に確立、それに加えて、段仕込み・火入れ・乳酸発酵など、現代の酒造りの原型が確立されたのが500年前だと言われています。
今回、伝統的と現代的を比較する上で、約500年前の1500〜1900年(室町時代〜明治中期)を伝統的とし、1900年(明治後期、戦後)以降を現代的として考えていくことにしましょう。
寒造りから四季醸造へ ─ 酒造りの季節を超えた進化
寒造りとは、一年で気温が下がる11月頃〜3月頃に行われる酒造りのことです。
元々、江戸時代初期まで年間を通して行う四季醸造が一般的でしたが、夏場の温度で発酵中の醪に雑菌が増殖し大量の米が無駄になることが多々あった様です。
また、米の不作により江戸幕府が酒造制限を行ったことで、冬場以外の酒造りが禁止になり寒造りが広まりました。
これにより、米の年間収穫量に合わせて新酒を造る流れができ、また腐敗の心配が比較的少なく安全に酒造りを進めることができるようになりました。
それに加えて、夏場に農業をする人々が冬場の閑散期に出稼ぎにくることで、杜氏制度が確立されました。
1960年代になると、大手酒造メーカーが年間を通して酒造りができる四季醸造蔵を完成させました。
四季醸造を行うためには、外気の温度変化に影響を受けない管理ができる施設が必要で、研究と当時の先端技術を駆使し現実となりました。
四季醸造をすることによって、年間を通して人員を確保できることや、一回で仕込む量が少なく済むため、その都度理想の酒質に近づけ易くなります。
しかし、冷房設備が整っていたとしても外気の影響は少なからずあり、醪の温度管理が難しいこと、設備投資が必要であることから寒造りを行う蔵もまだまだたくさんあります。
それぞれの蔵の規模や環境、目指している酒質によって、寒造り(伝統的)か四季醸造(現代的)に分かれている様です。
手作業から機械化へ ─ 変わる造り手と受け継がれる技
伝統的な酒造りは、当然の事ながら全て手作業で行われていたことは想像できるかと思います。
基本的に、連続蒸米機・放冷機・サーマルタンク(冷却装置付タンク)・圧搾機など全ての工程で機械化が現実化しているものの、多くの蔵は一部を機械化その他は手作業をしたりと、全てを機械に頼る蔵はまだまだ少ないように感じます。
特に、ユネスコ無形文化遺産に登録された「伝統的酒造り」で対象となった麹造り(製麹)は、最も手作業で行われる工程のひとつです。
麹菌は生き物であるため、毎回同じ様に造ったとしても、温度変化や発酵具合がその時々で異なります。
一度に造る量が多い場合は、かき混ぜる作業を自動製麹機に頼ることはあっても、最終的には人の手の感覚や香りで米麹の出来具合を判断する必要があることから、機械化が可能であっても、より良い酒造りを目指すには手作業が好まれていることが多いです。
一方、麹造りとは反対にどの酒蔵でも完全機械化しているのが精米です。
明治以前の精米は足踏精米または水車精米が主流で、明治に入ってもしばらくこの方法が続きます。
その後、機関車の動力を利用した精米機が広まり多くの酒蔵が採用し始めたことにより、足踏・水車精米が姿を消していきました。
その後、精米技術はさらに進化し、1900年頃に国内でも動力式精米機が発明されたことで、より高度で精密な精米機が次々と誕生し、現代の竪型精米機に至ります。
こういった産業技術の進化と共に、手作業から機械化に完全移行したことで、今まであまり磨くことの出来なかった米をより小さく磨くことが可能となりました。
一般的に精米歩合70%が酒造りの標準と言われていますが、現代技術を使えば0.数%、つまり1%より小さく削るまで出来ることには驚きです。
こういった酒造技術のおかげで、今まででは考えることの出来なかった新しい多種多様の日本酒が生まれるのです。
技術革新が生んだ日本酒の味わいの多様化
精米歩合が変えた酒の風味と個性
技術進化による機械化は効率化や生産量増加だけではなく、味わいにも大きく影響しています。
動力精米機が誕生する以前の精米は玄米をわずかしか磨くことが出来なかったため、米外部の栄養素の味わいが非常に強い、濃醇な酒質が一般的でした。
また発酵中に米が溶けにくく、タンパク質や糖分がまだ多く残っているため甘口で濃い味醂の様な味が特徴的だった様です。これが江戸時代に飲まれていた日本酒です。
その後、1900年代頃になると動力精米機が誕生し、米内部のでんぷん質付近まで磨くことがで可能になり、比較的米外部の複雑味が少ないものが生まれました。
そして1930年に竪型精米機が登場したことにより、飛躍的に精米技術が上がり、精米歩合50%つまり大吟醸クラスの淡麗な味わいの日本酒が造られる様になりました。
日本酒の味わいは精米歩合の影響が大きいため、違った精米率で米を磨くことで、淡麗から濃醇まで幅のある種類を楽しめる点が昔の日本酒とは異なることがわかります。
長期低温発酵による吟醸香の確立
今では主流である香り高いフルーティーなタイプは、伝統的酒造りでは行われていなかった長期低温発酵によって生み出されます。
清酒酵母は低温で時間をかけて発酵させることで果実や花の様な香り豊かな風味を生成する特徴があります。
一般的に酵母は25℃程度で最も発酵が活発になりますが、日本酒造りでは比較的低い温度でゆっくり時間をかけて、雑味の少ない味わいに仕上げます。
純米酒・本醸造などの香りが少ないものは、最高温度12〜13℃で約24日間かけて発酵させるのに対して、長期低温発酵では最高温度を10℃程度に抑え、30日以上かけて発酵させます。
長期低温発酵は酵母にとって過酷な状況で、ストレスをかけることで香り高い日本酒ができるという酵母の特徴を活かしたのが長期低温発酵です。
長期低温発酵が一般的になったのには、いくつかの理由があります。
まずひとつが、先ほどにもあった精米技術の進化です。
精米技術が進化し、軽い味わいが人気になったことで次に影響し始めたのが香りです。
精米歩合が高くなったことによって、米の味わいが比較的少ないスッキリとした味わいが人気になり、それと同時に香りも重要視される様になりました。
一般的に精米歩合が低いものには低温発酵は行わず、米本来の味わいを活かす発酵が主流で、反対に精米歩合が高いものには米の味わいが少ない分、香りを活かす必要があるため、長期低温発酵が必ずと言っていい程行われます。
もうひとつの理由は、1911年に始まった全国新酒鑑評会です。
鑑評会では日本酒の品質向上を目的とし、全国の酒蔵が技術力を競い、金賞等の入賞を目指す日本酒のコンテストです。
評価基準は味のバランスはもちろんのこと、香りつまり吟醸香の強さや種類なども点に繋がります。
1980年後半頃から新酒鑑評会で吟醸香が高く評価され始めたことをきっかけに吟醸ブームが起こり、多くの酒蔵が次々に吟醸系の酒造りを始め、今まで日本酒をあまり飲まなかった層や女性、そして若い世代にも受け入れられ人気が高まりました。
蔵付き酵母から協会酵母へ ─ 安定と多様性の両立
酵母はアルコール発酵において必須ですが、現在広く分布されている協会酵母や培養酵母ができる以前は、それぞれの蔵に住み着く蔵付き酵母に頼った酒造りが行われていました。
発酵中に樽から飛び散った酵母は、蔵建物内の壁や床、道具などのあらゆる場所に住み着き、その他の雑菌や微生物と混じり合い淘汰されます。
やがて生き残った酵母のみがその蔵の主となり、住み着くという仕組みです。これを酵母無添加と捉えます。
それぞれの蔵の酵母は特徴が少しずつ異なり、様々な微生物の中で生き抜いた酵母は発酵に強く、酸と味わいがしっかりとした力強い酒に仕上がります。
しかし、蔵付き酵母による酒造りはときに不安定で、良い酒ができるときもあれば、販売できない程の不味い酒に仕上がることもあったようです。
そこで1906年、日本醸造協会は安定した良い酒造りをする蔵から優良な酵母のみを採取・培養し、全国の酒蔵に分布する仕組みを作りました。
それが協会酵母の始まりです。当時、国の税収の割合を占める酒税をより多く徴収するために、日本酒業界全体の技術向上を目指しました。
協会酵母の他にも、個々の蔵で独自に培養した酵母(蔵付き酵母ではあるが無添加ではない)、各都道府県の工業技術センターが分布する酵母、大学の研究機関が分離した酵母など、その種類は1000を超えます。
協会酵母で造った日本酒は長期低温発酵に向き、香り華やかなものが非常に多く、酵母無添加と比較するとアルコール発酵が弱く度数が低くなり、繊細ですっきりと飲みやすいものが多く造られています。
今では幅広い層に楽しまれているこういった人気の商品も、日本酒の歴史から考えば非常に新しく、昔は解明されていなかった微生物の発酵など、科学的な面から進化した、現代の日本酒造りの象徴とも言えます。
伝統と革新が織りなす日本酒造りの未来
今回の記事では、伝統的酒造りがユネスコ世界文化遺産に登録されたことで、現代と昔ながらの酒造りを改めて比較できる良い機会となりました。
日本酒造りは歴史が長く、時代背景や技術進歩の影響で現在に至るまで、大きく変化してきました。
気温が低い冬場(11〜3月頃)のみ、それ以外の暑い時期は、醪の温度変化のコントロールが難しいため酒造りは行わず農業を主な仕事とする。
ほぼ全ての工程を手作業で行い、精米技術もまだ乏しかったため、酒質は米の味わいがしっかり残った濃醇タイプが一般的。
また、長期低温発酵の技術や考え、協会酵母がまだなかったため蔵付き酵母による発酵、香りは穏やかで吟醸香はない。
外温度の影響を受けない設備を完備し、四季醸造ができる様になり、夏場でも醪の腐敗の心配が少なく酒質が安定する。
また、蔵人たちは冬場のみの出稼ぎではなく通年雇用になる。
機械に頼れる酒造りにより生産量の増加、効率化や重労働の軽減に繋がる。精米技術の進歩の影響が大きく、超高精米タイプの飲みやすい淡麗タイプが増える。
高精白米や新酒鑑評会の影響により、吟醸系の日本酒が人気を博する。協会酵母の分布により酒造りが安定し、また香り・味が多様化する。
昔と今の酒造りは多くの相違点がありますが、伝統的な方法があればこその現在の酒造りです。
昔の人々が生み出した酒造りの仕組みや考えが基盤となり、現代の考えと組み合わさり新たな日本酒が生まれます。
最近では、木桶造りや酵母無添加、また生酛・山廃造り(記事:酛造り③ 参照)などの伝統的な酒造りのみをを行う蔵や、現代の造りから昔の造りにあえて戻す蔵も増えています。
数百年前ではおそらく考えもしなかった様な造り、味わいの日本酒が現在あるように、まだ想像もできない様な日本酒に将来出会えるのが楽しみです。

大阪出身の酒ソムリエ(Sake Diploma)
日本酒好きが高じて蔵人として酒造りを経験。日本酒の魅力の多くの人に伝えるため日々活動中。